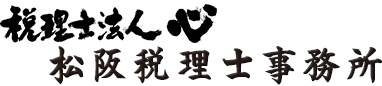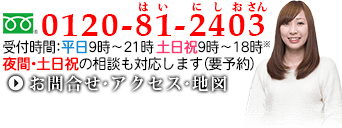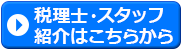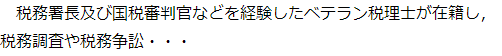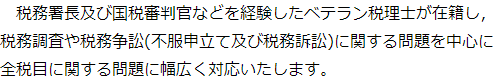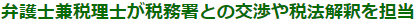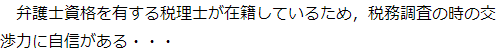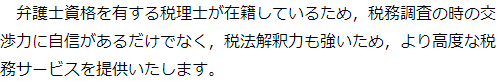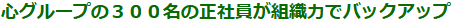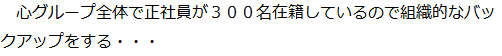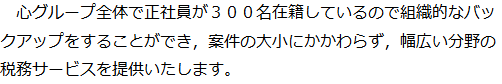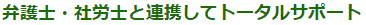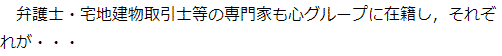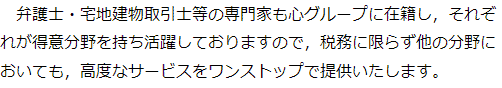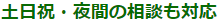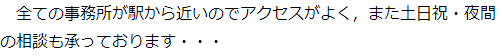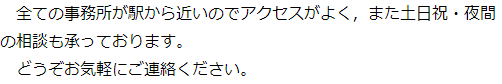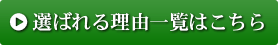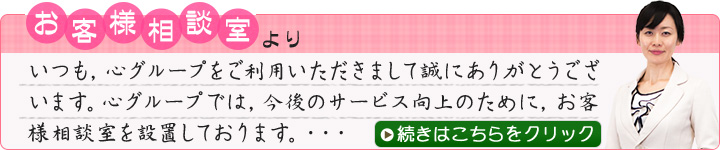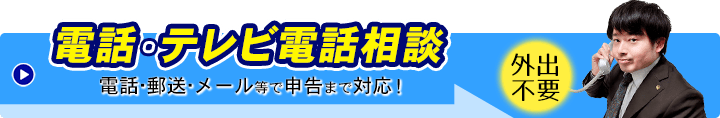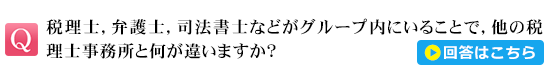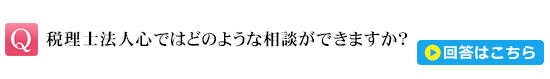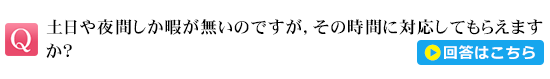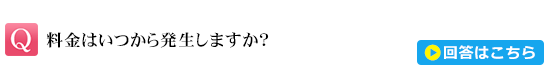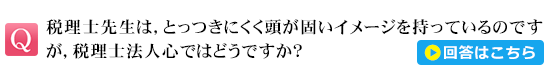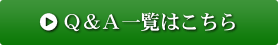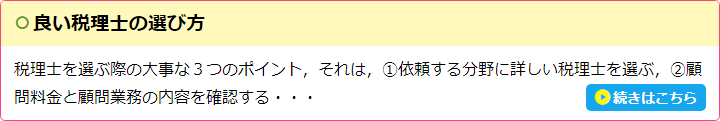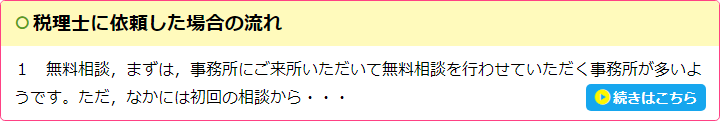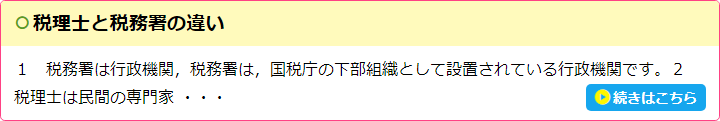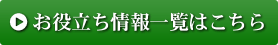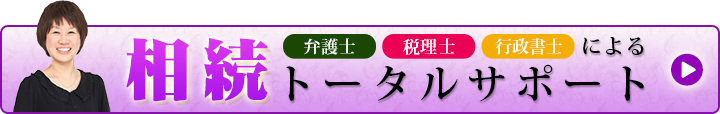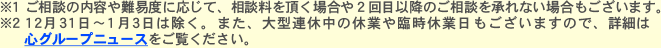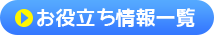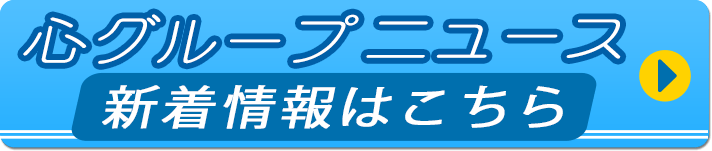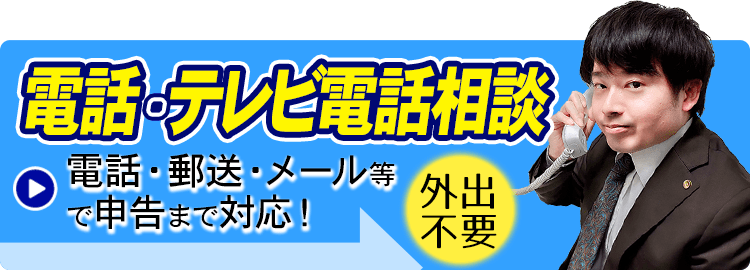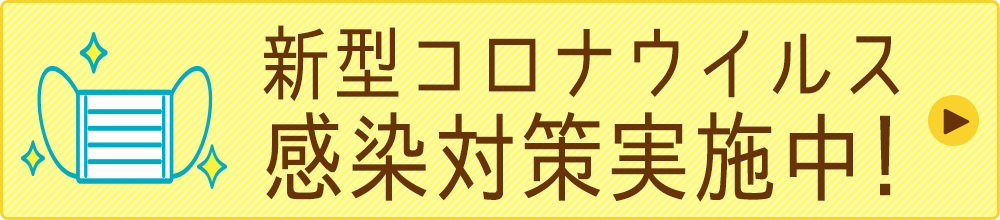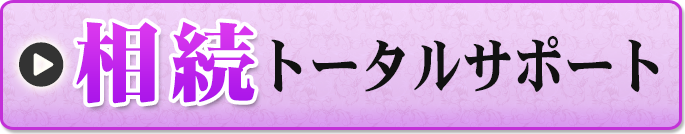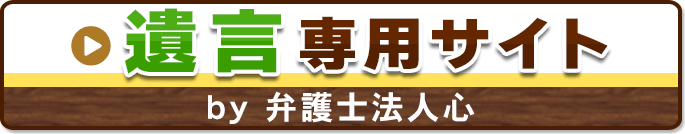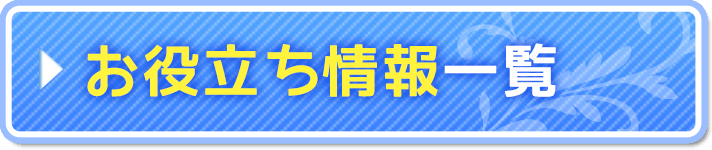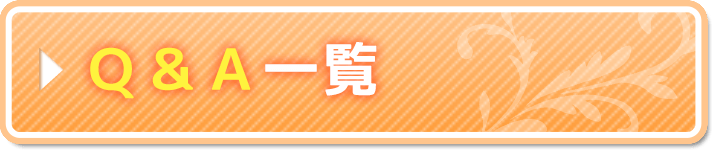松阪駅近くの税理士事務所です
こちらでは,松阪の事務所の周辺地図や駐車場情報をご覧いただけます。ご連絡用の電話番号なども記載しておりますので,ご確認ください。
顧問税理士と契約することのメリット
1 継続的に関与してもらうことができる

顧問税理士を契約すると、継続的に関与してもらうことができます。
このため、ある問題意識があると、その問題意識を引き継いで対応してもらうことができます。
たとえば、税額を軽減するため、一定の特例措置を利用することがありますが、税理士が継続的に関与していると、特例措置を更新すべき時期には、更新の手続を忘れずに取るよう、助言してもらえることがあります。
また、相続対策で、毎年、生前贈与を行っている場合も、毎年、税理士から、そろそろ生前贈与をした方が良いのではないか、今回の生前贈与ではこの財産を贈与するのが有効ではないかといった助言をしてもらうことも考えられます。
こうした、継続的な問題意識に基づく対処を行うべき場合には、継続的に同じ税理士が関与し、助言等を受けるのが望ましいと言えます。
他にも、普段の記帳では、取引の種類、慣行等を踏まえて、どのような処理を行うべきか、複数の処理方法が存在することがあります。
このような場合には、どの処理方法を用いても良いものの、一度ある処理方法を用いると決めた場合は、継続的に同じ処理方法を用いることが望ましいと考えられます。
たとえば、個人用と事業用の両方に用いているものの費用(水道光熱費等)について、家事按分により、何割を事業の経費として計上できるかについては、利用時間をベースに按分する方法、利用面積をベースに按分する方法等、様々な処理方法があります。
いずれの家事按分の方法を用いても、誤りとは言い難いですが、継続的に同じ家事按分の方法を用いるべきであると言うことはできます。
このように、継続的な処理方法を用いるべき場合には、継続的に同じ税理士が関与し、会計指導等を受けるのが望ましいと言えます。
2 いつでも相談することができる
顧問税理士を契約していると、記帳等で迷うことがあった場合には、いつでも相談することができます。
税理士にもよりますが、電話一本で会計事務所に相談を行い、毎回の疑問点を解消してもらうといったサービスを受けることも期待できます。
3 経営の方針について相談することができる
税理士によっては、経営の方針についての相談を行うことができることがあります。
たとえば、多額の設備投資を行うべきかどうか、行うとして、いつ、何回に分けて行うべきか、設備投資の原資を何にすべきか等について、税理士に相談することがあると思います。
このような相談は、継続的に関与し、売上や経費の推移、過去の申告内容等を把握している税理士でなければ、適切に回答することは困難でしょう。
継続的に関与している顧問税理士であればこそ、経営に関する相談を行うことができると言えます。
こうした相談を行うことができる点も、顧問税理士と契約するメリットの1つであると考えられます。
税理士への無料相談を検討中の方へ
1 無料相談を行っている税理士は増えている

近年では、無料相談を行っている税理士が増えています。
かつては、税理士への無料相談ができる場面は、確定申告期等の会場での相談等に限られていましたが、近年では、個人の事務所でも、無料相談を行うところが増えてきています。
無料相談は、どのような目的で行われているのでしょうか?
その目的の1つは、税理士に依頼するハードルを下げることにあります。
有料相談になると、費用負担が生じますので、試しに相談してみようという気にはなりにくく、税理士に相談するハードルが高まります。
複数の税理士に相談し、どの税理士に依頼するかを決めることもやりにくくなるでしょう。
無料相談であれば、費用負担が生じませんので、試しに税理士に相談するハードルが低くなり、複数の税理士の中から依頼する税理士を探すことも、より容易になってくるものと思います。
2 無料相談の注意点
無料相談を行う際には、無料相談の枠内で正解を見つけようとすることは、なるべく避けた方が良いものと思います。
無料相談については、相談時間が30分等に限定されていることが多いと思います。
限られた時間になりますので、相談の間に共有できる情報には、限界があります。
限られた情報から、正確性の高い回答を行うことは、困難を伴います。
このため、無料相談の範囲内で、精度の高い「正解」を求めることは、一般的には困難です。
無料相談では、限られた情報を踏まえての回答がなされるに過ぎないことに注意しましょう。
無料相談では、むしろ、相談を担当している税理士が信頼できるかどうか、自分にとって合う税理士かどうか等を確認することを、主たる目的とした方が良いのではないかと思います。
この点で、無料相談は、どの税理士に依頼するかを決めるための場としては、積極的に活用できる場面であることとなります。
3 当法人へのご相談
当法人でも、原則として初回相談料は無料でご相談をお受けしています。
まずは試しに税理士に相談してみたいという方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。
税金について税理士に相談するべきタイミング
1 税理士に相談するべきタイミング

税金の問題が生じる場面には、様々なものがあります。
ここでは、それぞれの税目について、税理士に相談するべきタイミングを説明したいと思います。
2 所得税、法人税の場合
所得税、法人税については、普段の業務の過程でどのような記帳を行うかが重要になってきます。
このため、普段の記帳の段階から、迷うことがあれば、税理士に相談した方が良いでしょう。
また、申告書の際にも、どのような申告書を作成すべきかが問題になってきます。
このため、申告書の提出前に、税理士に相談すべき場面が生じてくることがあります。
申告期限(所得税だと3月15日、法人税だと決算期末)の直前だと、十分な相談を行うことができない可能性がありますので、申告期限前に余裕をもって税理士に相談するのが良いでしょう。
3 相続税
相続税については、十分な資料の収集、取りまとめ、検討のため、まとまった時間が必要になります。
相続税の申告期限は、相続が起きたことを知ってから10か月後とされていますが、申告の準備を十分に行うため、前倒しで準備を行うのが望ましいです。
このため、税理士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう。
もちろん、申告期限の直前のご相談であっても、一旦はお手持ちの資料で申告を行い、必要な場合には、後日、申告をし直すといった対応も考えられますが、やはり、十分な準備を行った上で申告を行うのが望ましいです。
4 贈与税
贈与税については、申告の準備に要する時間は、比較的短いです。
しかし、贈与税については、納付すべき税額が多額になることがあり、納付資金の調達等について、検討を行うべき場合があります。
また、贈与税については、何らかの特例を用いることにより、納付すべき税額を大幅に減少させることができることがありますが、このような特例適用の可否については、十分に検討を行っておいた方が良いでしょう。
これらを踏まえると、贈与税については、贈与の計画を立てた段階で、早めに税理士にご相談いただくのが良いでしょう。
税金について税理士に相談すべきケース
1 手続を行えば税金が軽減されることがある

給与収入や年金収入で生活している場合は、税金のことを意識する場面はほとんどないのではないかと思います。
たとえば、給与収入については、源泉徴収と年末調整により、会社が税金の計算を行い、源泉所得税の納付、修正等の対応を行います。
これらの制度だけで対処が可能な場合は、税金のことをほとんど意識することなく、税金の処理後完了することとなってしまいます。
もっとも、一定の場合には、手続を行うことにより、源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。
このような場合には、税理士等にご相談の上、確定申告の手続を行うことを検討するべきでしょう。
以下では、手続を行うことにより、所得税が還付される例を挙げたいと思います。
2 住宅ローンを組んだ場合は、税金が還付される可能性がある
住宅ローンを組んで、住宅を新築、取得、増改築した場合には、住宅ローンの年末残高の1%が、10年間に渡って、所得税から差し引かれることとなります。
なお、建物部分について、10%の消費税を納付した場合には、住宅ローン控除の期間が3年間延長されます。
このため、確定申告を行えば、住宅ローンの年末残高の1%が、少なくとも10年間に渡って、還付されることとなります 。
たとえば、住宅ローンの年末残高が1000万円でしたら、1%にあたる10万円が還付されることとなります。
このように、まとまった金額が10年に渡って還付されることとなりますので、かなりの税金が還付される可能性があります。
住宅ローン控除を用いるには、住宅ローンの期間が10年以上である、住宅の床面積が一定以上である、総所得が3000万円以下 (ただし、住宅の床面積が40㎡~50㎡の場合は、1000万円以下)である等、一定の要件を満たす必要があります。
そして、住宅ローン控除を用いるためには、必ず、初年度に確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わなければ、住宅ローン控除を用いることはできなくなってしまいます 。
3 税理士へのお問い合わせ
このように、税金を軽減する制度を用いるために、確定申告を行う必要がある場合があります。
当法人は、初めての確定申告についてのご相談もお受けしていますので、税金に関するご相談をご希望でしたら、当法人までお問い合わせください。
相続対策と税理士
1 税理士が行う相続対策

相続対策に関係する専門家と言うと、税理士を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。
もっとも、税理士が具体的にどのような相続対策を行っているのかについては、イメージが湧きにくいのではないかと思います。
ここでは、税理士が行う相続対策について、いくつかの具体例を挙げたいと思います。
2 財産の総額の減額
相続税は、被相続人が相続時点で有していた財産について、課税されます。
相続時点で有していた財産が多ければ多い程、相続税の税率は高くなりますし、相続税の額も大きくなります。
このため、相続までに、被相続人が有している財産の総額を減額することができれば、相続税を減額することができることとなります。
たとえば、被相続人が会社経営者であり、非上場会社の株式を有している場合、非上場の株式もまた、相続税の課税対象になります。
被相続人が会社に対して代表者貸付を行っている場合は、会社に対する貸付金もまた、相続税の課税対象になります。
このような場合には、会社の株式や貸付金をどのように評価するかが問題となります。
貸付金については、基本的には、額面どおりの金額を、相続財産として評価する必要があります。
このように、被相続人が経営している会社一つをとっても、様々な場面で相続対策を行うことが考えられます。
3 非課税となる特例の利用
相続財産に該当するとしても、非課税の特例を用いることにより、相続税の課税対象から除外することができる場合があります。
たとえば、死亡退職金については、500万円×相続人までは、相続税が非課税とされています。
このため、相続人の誰かが死亡退職金を受け取るものとしておくことにより、会社の株式の価値を下げることができるとともに、死亡退職金への課税を避けることができます。
4 税理士への相続対策のご相談
このように、財産の評価額を減額したり、非課税の特例を利用できるようにする手法は様々です。
税理士は、このような様々な手法から、適切な相続対策を提案することができます。
相続対策についてのご相談がありましたら、税理士までお問い合わせください。
各専門家が協力できることの強み
1 税理士が他の専門家と連携すべき場面

税理士が他の専門家と連携すべき場面は、しばしばあります。
このような場合には、他の専門家と連携して対処することができる税理士の方がスムーズに問題に対処することができるでしょう。
ここでは、税理士が弁護士と連携すべき場面について、説明したいと思います。
2 弁護士と連携すべき場面
税理士が申告書を作成した場合に、後日、税務署からの指摘がなされ、申告内容の修正を求められることがあります。
税務署からの指摘が正当であれば、その指摘に基づき、自主的に修正申告を行う流れになるでしょう。
他方、税務署からの指摘が不当である場合には、これを争うべき場合があります。
税務署が、不当な指摘を前提として、課税処分を行った場合には、審査請求により、上級の国税庁に対し、不服の申立を行うこととなります。
さらに、国税庁が不服を認めなかった場合には、裁判所で裁判(税務訴訟)をし、税務署の課税処分を争うことができます。
このように、審査請求や税務訴訟を行う場合には、法律の専門家である弁護士と連携しなければならない場面が出てきます。
このような場面で、税理士と弁護士が適切に連携できるかどうかは、審査請求や税務訴訟の結果を大きく左右することがあります。
税理士に相談する際は、他の専門家のサポートが必要になる可能性もふまえて、専門家同士の連携がとれている税理士を選ばれることをおすすめいたします。
遺言についてお悩みの方へ
1 税理士の仕事と遺言

多くの場合、遺言については、法律の専門家である弁護士等に相談がなされるでしょう。
しかし、現実には、税理士の仕事の中で、遺言が関係してくる場面があります。
今回は、どのような場面で遺言が関係してくるかについて、説明したいと思います。
2 相続税の生前対策
生前に、相続税の生前対策を行っておきたいというご相談を受けることが、しばしばあります。
このような場面では、所有している財産の評価額を下げる、生前贈与を行う、生命保険に加入する等の対策が行われることが多いですが、合わせて、遺言を作成しておき、どの財産を誰が取得するかまで決めてしまうことも多いです。
このように、あらかじめどの財産を誰が取得するかまで決めておくことによって、相続の場面で紛争が生じるリスクを下げることができます。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等、税負担の軽減に繋がる一定の制度を利用するために、遺言によって、どの財産を誰が取得するかを確定しておいた方が望ましいこともあります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等を用いるためには、対象となる遺産を誰が取得するか確定している必要があります。
遺言によって、誰がどの財産を取得するかをあらかじめ決めておけば、相続開始後に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用をスムーズに受けることができることとなります。
以上のとおり、生前対策の場面では、税理士の仕事に遺言が関係してくることがしばしばあります。
3 税理士に相談する場合の注意点
このように、遺言が関係する問題について税理士に相談する場合には、注意すべきことがあります。
それは、税理士は、税金の専門家であって、法律の専門家ではないということです。
遺言を作成する際には、法的な知識が必要になりますので、法律の専門家である弁護士等が関与した方が望ましいことが多いです。
以上から、遺言の問題が出てくる場合は、税理士と弁護士等が連携している事務所にご相談いただくのが良いでしょう。
申告までにかかる時間の目安
1 申告までにかかる時間は税金の種類によって変わってくる

税金には、様々な種類があります。
代表的なものとしては、所得税、法人税、相続税、贈与税等があります。
そして、税金の種類によって、申告書の内容や提出すべき書類は大きく異なってきます。
このため、税金の申告までにかかる時間は、税金の種類によって大きく異なります。
ここでは、相続税について、申告までにかかる時間の目安を説明したいと思います。
2 税理士が相続税申告書を作成するのに必要な時間
きちんとした申告を行う場合、相続税の申告にかかる時間は、少なくとも1~3か月は見込んでおいた方が良いでしょう。
相続税の申告にあたっては、相続した財産や債務を余すことなく列挙する必要があります。
その上で、個々の財産について、評価額の計算を行う必要があります。
そして、こうした計算過程を税務署に報告するため、評価のための膨大な資料を作成する必要があります。
これらのすべてを完了させるためには、少なくとも1~3か月の時間は見込んでおいた方が良いでしょう。
また、遺産分割を完了している前提で申告を行う場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付する必要もあります。
とはいえ、現実には、様々な事情から、申告期限まで間がないものの、申告書を完成させて提出しなければならない場合もあります。
たとえば、相続人全員の意見がまとまるまで時間がかかり、申告の相談をするのが申告期限の直前になったということも起こり得るでしょう。
このような場合は、短期間で、手持ちの情報だけで、申告書を作成、提出し、後日、修正すべき点があった場合は、修正申告書を提出するといった対処を行うこともあります。
3 税理士への早めのご相談を
やはり、申告に際しては、最初からきちんとした申告書を作成、提出するのが望ましいと言えます。
申告についての相談は、申告期限に間に合うようにするためにも、お早めにご相談いただいた方が安全でしょう。
税理士を依頼する場合の税理士の選び方
1 税理士の選び方とは

税理士を依頼する場合の税理士の選び方には、どのようなものがあるのでしょうか?
この点は、税理士に依頼するニーズによっても変わってくるところですが、以下の点がポイントになってくるものと思います。
2 税制改正に対応
課税のルールは、税制改正により、毎年のように変更されています。
このため、税理士は、税制改正の内容を把握し、現時点で適用される制度の内容を正確に把握しておかなければなりません。
たとえば、経費計上のルールが国税庁によってしめされることがあります。
このようなルールが変更され、旧来は経費計上できたものが、新しいルールでは経費計上することができなくなってしまうことがあります。
例を挙げると、令和元年7月以降、法人の保険料の経費計上のルールが変更され、経費計上の対象となる保険料が制限されることとなりました。
このようなルールの変更があったにもかかわらす、旧来のルールに基づく経費計上を行うと、過少申告となり、後日、税務調査で指摘がなされ、加算税や延滞税を納付しなければならなくなるおそれがあります。
この点を踏まえると、税制改正に確実に対応している税理士に依頼しなければならないことが分かります。
3 経営判断の資料の作成に対応
税理士は、申告を行ったり、税務調査対応を行ったりすることだけが仕事ではありません。
会社の経営判断するにあたって必須の資料をもっているのが税理士です。
税理士は、経営のパートナーとして、経営判断の資料を作成することも望まれます。
たとえば、毎年の決算書だけてはなく、売上の推移等から経営状態な今後の事業の見通し等を記載した、経営診断レポートの作成に対応している税理士もいます。
このような資料の提供を受けることができれば、経営判断に資することとなるでしょう。
このように、経営判断の資料の作成にも対応している税理士への依頼が望まれる場合もあるでしょう。
4 税理士を依頼する場合の税理士の選び方
どのような税理士に依頼するべきであるかは、税理士を依頼するニーズによっても変わってくるところですが、代表的なポイントは、以上のとおりだと思います。
これらのポイントを踏まえつつ、信頼のできる税理士に依頼したいところです。
税理士に相談する際の窓口と相談の流れ
1 税理士への相談

税理士に相談したいことがあったとしても、まずはどこに問い合わせを行えばよいのかは迷いどころだと思います。
税理士に相談するのが初めての方は、特に迷われるかと思います。
ここでは、税理士に相談するときの窓口を紹介し、それぞれについて相談の流れを説明したいと思います。
2 商工会議所、自治体、税理士会等の相談会の利用
地方によりますが、商工会議所、自治体、税理士会等で、相談会を設けていることがあります。
こうした相談会では、相談枠が設けられ、税金に関する質問を行うことができます。
こうした相談会は、30分程度の相談枠を利用することとなり、時間的な制約があります。
相談時間が限られていますので、限られた時間で簡潔に相談ができるよう、あらかじめ相談内容や資料をまとめておくことをおすすめします。
また、限られた時間での回答になりますので、回答内容も、一般的に考えた場合の内容にとどまりがちです。
ご自身の具体的事情へ立ち入った回答や、継続的な関与をお求めの場合は、個別の税理士との間で相談を継続することとなるかと思います。
3 税理士の事務所への相談
税理士の事務所に問い合わせ、相談を行うことも考えられます。
この場合、相談のための費用が発生することが多いですが、近年では、初回相談を無料とする事務所等も出てきています。
個別の税理士への相談となりますので、継続して相談し、一般論ではなく、具体的事情に立ち入った回答を求めることも可能でしょう。
また、帳簿作成の代行や申告書の作成等の継続的な関与を依頼することもできます。
税理士が関与する範囲、費用等を協議し、正式に税理士と契約締結となれば、税理士が代わりにこれらの仕事を進めていくこととなります。
4 税理士へのご相談
このように、継続的な関与をお求めの場合は、税理士の事務所へお問い合わせいただいた方がよいかと思います。
当法人は、初回相談を原則無料としていますので、税金についてお困りのことがありましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。
税金で困った場合の相談先について
1 税金について相談する2つの場面

税金についての相談をしたい場合は、誰に相談するのが良いのでしょうか?
税金についての相談といっても、色々な場面での相談があり得ます。
ここでは、2つの場面について、誰に相談するのが良いのかを説明したいと思います。
2 記帳で判断に迷ったとき
日々の業務の過程では、入出金記録や請求書、領収書等の原資料から、帳簿を作成しなければなりません。
帳簿を作成することを、記帳と言いますが、記帳の場面では、仕訳の方法をどうするか、どこまでを経費として計上するか等で迷うことが多いでしょう。
記帳で迷った場合は、誰に相談するのが良いのでしょうか?
1つ目の相談先として、国税庁の電話相談や税務署での面談相談が挙げられます。
これらは、費用負担なく利用することができます。
ただ、国税庁や税務署は、個別の質問に対して、一般的な事項を回答するにとどまりますので、あらかじめ、質問内容を自分でまとめておいた上で、相談を行う必要があることとなります。
また、帳簿の作成自体は、自分で行う必要があります。
2つ目の相談先として、税理士への相談が挙げられます。
どのような形で相談できるかは、税理士との契約によっても異なります。
たとえば、入出金記録、請求書、領収書等の原資料を定期的に税理士に送付し、税理士の方で仕訳を行い、帳簿を作成するといった形で、包括的に記帳を依頼することもできます。
3 申告書を作成しなければならないとき
税金との関係では、最終的には、申告期限までに申告書を作成、提出しなければなりません。
申告書の作成方法については、国税庁のホームページ等に解説がありますが、難解な用語を用いていることが多く、具体的な場面でどのように当てはめれば良いのか分からないことも多いと思います。
このように、申告書の作成について相談したい場合は、誰に相談するのが良いのでしょうか?
申告書の作成についても、記帳代行とほぼ同様に考えれば良いでしょう。
国税庁の電話相談や税務署については、基本的には、あらかじめ質問内容を自分でまとめた上で相談を行う必要があるでしょうし、申告書の作成も自分で行わなければなりません。
税理士については、契約内容次第では、原資料を税理士に送付し、税理士の方で取りまとめを行い、申告書を作成するといった形で、包括的に申告書の作成を依頼することもできます。
4 税金についての相談先
結論としては、適切な相談先は、自分がどのような関与を必要としているかによって変わってきます。
記帳も申告書の作成も、おおむねの部分を自分でしてしまう前提でしたら、国税庁の電話相談や税務署での面談相談でも対応可能でしょうし、包括的に任せる前提で相談するのでしたら、税理士に相談するのが良いでしょう。
税理士選びのポイント
1 どのように税理士を選ぶべきか

税理士によって得意分野というのは様々です。
例えば、法人向けの会計・税務や経営のアドバイス等を得意とする税理士もいれば、個人向けの節税を得意とする税理士、税務調査を得意とする税理士などもいます。
税理士に依頼する際には、目的に応じて、期待する内容を得意とする税理士に依頼することが大切です。
2 税理士との相性
税理士を選ぶ際には相性も重要です。
特に法人や個人事業主の方の場合は、税理士とは長い付き合いとなるため、信頼して相談できる税理士を選ぶことをおすすめします。
無料相談を行っている事務所も多いため、その機会を活用し、実際に相談してその税理士との相性を確かめてみるとよいかと思います。
3 サービス内容と税理士費用
税理士によってサービス内容が異なります。
最低限の税務申告のみを行う税理士もいれば、会計や経営のコンサルティングまで行うような税理士もいます。
当然費用も異なってきますので、税理士費用との兼ね合いで、どのようなサービスを求めるのかということを検討されるとよいかと思います。
4 当事務所へお気軽にご相談ください
当事務所では、法人だけでなく、個人の方の税務申告等も取り扱っております。
松阪で税理士をお探しの際は、お気軽にご相談ください。
不動産に強い税理士へ依頼するメリット
1 不動産が問題になる場面

税金の申告において、不動産の問題が出てくることは、しばしばあります。
例を挙げると、以下のとおりです。
① 所得税
不動産を売却した場合に、売却代金について、譲渡所得税が課税される可能性があります。
また、不動産から賃料収入が生じている場合は、基本的には、不動産所得について申告を行う必要があります。
② 相続税、贈与税
相続や贈与の対象になった不動産について、評価額を算定し、申告を行う必要があります。
このように税金の問題と不動産は、密接に絡んでくることがあります。
不動産が問題になる場面では、不動産に強い税理士かどうかによって、申告の内容が異なってくる可能性があります。
このため、税理士によって、納付する税金の金額が大きく異なってくることも起こり得るのです。
ここでは、不動産に強い税理士かどうかによって大きく変わってくる場面として、不動産の売却益に課税される譲渡所得税について説明したいと思います。
2 譲渡所得税の申告をしなければならないが、売買契約書がない
不動産を売却した場合には、売却代金について、課税がなされます。
所得税の税率は、長期譲渡所得で15%、短期譲渡所得で30%です。
このとき、かつて不動産を購入したときの価格が証明できれば、これを取得費として、不動産の売却代金から差し引くことができます。
かつて不動産を購入したときと比較して、低い価格でしか不動産を売却することができなかった場合は、譲渡所得税は0円になります。
このように、かつて不動産を購入したときの価格が証明できるかどうかによって、譲渡所得税の額は大きく変わってきます。
かつて不動産を購入したときの売買契約書が残っている場合は、売買契約書のコピーを添付して申告すれば、購入したときの価格を証明することができます。
とはいえ、多くの事案では、不動産を購入したのがかなり前であり、売買契約書が残っていなかったりします。
このような事例では、概算取得費として、売却価格の5%を差し引くことができるものの、わずか5%の差し引きでは、かなりの額の譲渡所得税が課税されることとなってしまいます。
そして、このような場合には、5%の譲渡所得のみを差し引いて、譲渡所得の申告がなされることが多いのが実情です。
しかし、実際には、売買契約書がなかったとしても、かつて不動産を購入したときの金額の手がかりを得ることができますし、このような手がかりを用いて申告することが認められる可能性もあります。
たとえば、分譲業者から不動産を購入した場合は、分譲業者が有している資料を用いることが考えられます。
また、不動産の購入に際して住宅ローンが組まれている場合は、住宅ローンの償還表や、登記簿の乙区欄の記載を参照することも考えられます。
こうした手がかりもない場合は、リスクがあるものの、市街地価格指数や建物の標準的な建築価額表を参照することも考えられます(ただし、これらの資料が有効な場合は、限定的に考えるべきでしょう)。
このように、不動産に強い税理士であれば、複数の情報収集手段を用いて、どのような申告を行うかを検討することができます。
税理士に依頼した場合の調査方法
1 税理士の調査方法

申告の際には、十分な調査を行い、漏れのない申告書を作成することが必要不可欠です。
調査に不十分な点があると、申告漏れが生じてしまい、本税だけでなく、加算税や延滞税を納付する必要も生じてしまいます。
このため、申告の際には、どのようにして十分な調査を行うかが勝負になってきます。
それでは、税理士は、どのようにして、申告のための調査を行っているのでしょうか。
ここでは、その概略を説明したいと思います。
2 資料の収集方法
申告に必要な資料の大部分は、お手元に届いている書類になります。
たとえば、年末には、勤務先や年金事務所から、源泉徴収票が届くものと思います。
源泉徴収票は、申告書を作成するに当たり、必要不可欠な資料になります。
他にも、医療費の明細書、保険料の控除証明書等も、必要な資料になります。
これらについても、1月前後に皆様のお手元に届くものと思います。
合わせて、1年間の収入や支出を漏れなく把握するため、通帳のご提供をお願いすることも多いと思います。
申告の際には、皆様からこれらのお手元に届いている資料をご提供いただき、申告書の作成を進めることとなります。
3 調査の方法
税理士は、これらの資料を確認した上で、必要な調査を行います。
調査については、多くの場合、皆様に聞き取りを行い、必要な情報を集めることとなります。
たとえば、通帳に誰かからの入金の記載がある場合、皆様に、どのような理由で入金がなされたのかを確認し、申告の対象になるかどうかを判断することとなります。
聞き取りによっても、さらに調査を行う必要が残る場合は、支払元、支払先に問い合わせ、情報の提供をお願いすることもあります。
合わせて、税理士は、法令の調査を行います。
申告のルールは、法令や通達によって詳細に定められていますが、その内容は複雑多岐にわたるものであり、すぐに回答を出すことができない問題もあります。
税理士は、必要があれば、その都度、法令や通達の調査を行い、ルールにのっとった申告書の作成を行っています。
財産評価に強い税理士に相談すべき理由
1 税理士による財産評価

税金の申告にあたっては、財産評価を行うべき場面は、しばしばあります。
こうした財産評価は、適切な評価方法によって行う必要があります。
税負担を軽くするため、意図的に過少な財産評価を行ってしまうと、後日、税務署から指摘がなされ、本税の追加分とともに、加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。
また、誤って過大な財産評価を行ってしまうと、本来納付しなくても良い税金を納付したこととなってしまいます。
このように、過少な評価も、過大な評価も、最終的に損失を生じさせるおそれがありますので、適正な財産評価を行う必要があります。
このような財産評価のルールは、財産評価基本通達等によって詳細に定められています。
しかし、財産評価基本通達等のルールに基づいて評価を行うことは、以下で述べるように、難しい作業になります。
ここでは、不動産の評価の難しさについて、説明を行いたいと思います。
2 不動産の評価の難しさ
不動産の評価が困難となるポイントは、いくつかあります。
そのうちの1つは、経験に裏付けられた気付きが必要となることにあります。
不動産の評価額を減額する要素の多くは、財産評価基本通達等で定められています。
しかし、こうした要素を実際に利用して評価できるかどうかは、別問題です。
たとえば、不特定多数人が利用する道路については、財産評価基本通達では、0円と評価するものとされています。
このため、公衆用道路については、上記を理由として、0円として評価を行うべきです。
航空写真等で、公衆用道路として利用されていることが明らかであれば、こうした気付きを得ることは容易でしょう。
それでは、宅地として利用している土地の端の部分が事実上公衆用道路として利用されている場合はどうでしょうか?
このような気付きを得るには、現地で境界標等を確認し、端の部分が事実上公衆用道路として利用されているとの気付きを得る必要があります。
そして、そもそも、土地の端が事実上公衆用道路として利用されている可能性を念頭に置いて現地評価を行わなければ、こうした気付きを得られることはないでしょう。
このように、不動産の評価については、経験に裏付けされた気付きが重要になることが、しばしばあります。
3 財産評価に強い税理士に相談すべき
こうした経験に裏付けされた気付きを得て、適正な財産評価に基づく申告を行うためには、財産評価に強い税理士にご相談いただくより他ないものと思います。